

ボランティアしませんか |
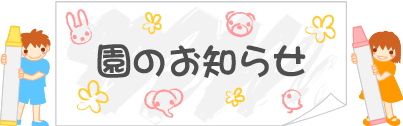
| 11月のお知らせ |
息を合わせる−2歳児(ちゅうりっぷ)がお昼寝用のゴザを、ともだちと協力しながら敷いているという話を担任から聞きました。自己主張の多い2歳児では無理だろうと思い、想像出来なかったのですが、ビデオを見せてもらい驚きました。担任の声かけで、子どもたちが見事に息を合わせてゴザを広げていたのです。  『みんなで息を合わせてゴザを広げる2歳児たち』 いつ頃から出来るようになったのかを記録を見直しながらまとめてもらうと、そのスタートは春から始まっていました。最初は担任がゴザを敷いているのを見て、興味を持った子どもが一人二人と交代でやってきました。その活動は気まぐれであったわけですが、それを横目で毎日見つめている子どもの姿もその背景にありました。保育者といっしょにやった子は「ありがとう」とお礼を言われ、嬉しい体験を積み重ねます。見ている子もだんだん心が揺り動かされ、自分から挑戦しようとやってきます。そんな活動が夏までずっと続いたわけですが、この毎日繰り返される保育者の活動に子どもが興味を持って、主体的に参加し、上手くいった喜びや感謝される体験を何百回も繰り返していることになります。そこはなかなか見えない教育の部分なのですが、振返ることによって私達も気づくことができます。それがだんだん実を結び、9月になるといっしょにやりたい子がだんだん増えていきました。するとそこで新たなトラブルが発生していきました。  『わたし、ぼく、どいて! こないで! だめ!』
トラブルというのは、参加する子どもが増えて、自分の場所を確保するのに争い、相手が勝手に引っ張ったり押したりするのが気に入らなくて、もう子どもだけでは収拾のつかない状態になったことです。そこに保育者が加わり、みんなに声をかけながら一緒にやることで、統制が取れてきます。この時いくら「ちゃんとしなさい」「あぶないでしょ」「友だちをおさないで」と言葉だけかけても混乱は続きます。そこに大人がいっしょにやりながら上手くいったという体験をつんでいくことが大切だと思います。よくケンカが大事だと言われますが、混乱の意味が解からない年齢でのトラブルは説得や叱責ではなく、ていねいな対応で、上手くいった喜びの体験が必要です。 稲刈りをしました。園庭の小さな田んぼでヤゴやメダカと一緒に育った稲の刈入れを3,4,5歳児が行いました。籾すりをして12月にいただきます。 
11月の行事予定
5日〜17日 ニコニコクッキング −手作りの喜び−10月27日(土) 給食室主催で『ニコニコクッキング』を実施し、3人の保護者の方と食育雑誌『食べもの文化』の編集者の方で料理を楽しみました。メニューは餃子、春雨サラダ、スイートポテトでしたが、参加した方々の家庭での料理体験が次々紹介され、様々な違いに驚いたり、発見があったりと、大変楽しい交流になりました。中でも餃子の包み方や、具材の違いなどで盛り上がり、最後には足りなくなった餃子の皮を小麦粉から手作りで作る体験にもつながり、とっても参考になりました。当初は給食の先生が講師になるはずでしたが、終わってみるとお互いに学び合う場になり、栄養士も大変参考になったと大喜びしていました。次回は来年度になりますが、ぜひ、体験していない人は、ご参加下さい。  『餃子の具材をやさしく混ぜることも大発見でした』 お知らせ
イベント案内(予約をしてください)
何でも気軽にどうぞ。臨床心理士への相談も予約により可能です。(保護者の方も可。) 緊急に保育が必要な方のお子さんをお預かりいたします。登録が必要です。 |
Copyright (C) 2013 八王子市立長房西保育園 |

